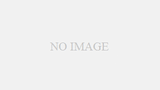かつて nskk.org に掲載してあった全国青年ネットワークニュースをarchive.orgより復刻しました。
全国青年ネットワークニュースのプリントを探しています。
第1号から9号のプリントや本文テキストも探しています。
お持ちの方はご連絡ください。
第15号 2000年11月23日発行
全国青年大会開催
「ひらこう!私を教会を」をテーマに、11の分科会
8月25~28日、東京YMCA野辺山高原センターで2000年日本聖公会全国青年大会が、同実行委員会の主催により開催された。
1992年に再開された全国レベルの青年の集まりも、今回で3回を数える。全教区から、また大韓聖公会、NCC関西青年協議会などから総勢140名の青年が集った。テーマは「ひらこう!私を、教会を~今、私たちの生活(いき)ているところから」。
初日は、開会礼拝の後、各教区単位による楽しい自己紹介。主題講演は、日本基督教団山谷兄弟の家伝道所の菊地譲牧師。菊地牧師は山谷でマリヤ食堂を作って日雇・野宿労働者に安い食事を提供したり夜回り活動をしたりしている。講演は、現代哲学を紹介しながら、言葉というものが恣意的なものであり別の視点からとらえかえす必要があること、無意識に刷り込まれた価値観を洗いなおす必要があること、などについてお話をされた。
分科会は「平和」「メディアと信仰」「ジェンダー」「地域の中の教会」「学校と教会」「カルト宗教」「礼拝」「礼拝音楽」「恋愛・結婚」「働くこと」「グローバリゼーション」という11の分科会。「平和」では非暴力ワークショップ、「メディアと信仰」ではホームページ作成、「働くこと」では十字架作り、「グローバリゼーション」ではロールプレイ、「ジェンダー」ではビデオを用いるなど、様々な工夫があり、楽しくまた真剣に語り合った。
交流会では体を動かして交流の時を持った。バイブルシェアリングでは、まず聖公会神学院の大町信也司祭によるお話し。主題聖句である「門をたたきなさい、そうすれば開かれる」について、イエス時代における門の意味について話された。私たちはこの言葉を、頑張ればきっと報われる、という感じで格言的に受け取りがちであり、驚くことはない。ところがイエスが、「門をたたきなさい」と言ったとき、民衆は「非常に驚いた」という。当時の人々はなぜそんなに驚いたのか?エルサレムは当時宗教的・政治的・経済的中心であり、そのエルサレムの門の中に入ることができなかった人たちがいた。皮なめし、屠殺業者、性労働者、肉食業者、皮細工人、賭博師…。差別されていたアウトカーストの人たちであった。イエスは門の中に入ることのできないそういった人たちに「門をたたきなさい」と言ったのである。「開く」というイメージを一新させられる話しであった。「地域に開かれた教会」とよく言われるが、閉鎖的な教会を地域に開こうということではなく、むしろ閉じた地域を教会が開いていく、というダイナミックな宣教の視座を与えられた。その後グループごとに主題聖句について語り合った。
「青年からの呼びかけ」では、大韓聖公会の青年で分かち合いの家の運動にもかかわっているパク・スンヒさんと、手話通訳の活動をされている小野幸さん(東京教区)からお話をうかがった。これら二つの教会での活動も社会で弱くされた人たちからこそ、閉じられた社会が切り開かれていく、というもので、様々な示唆が与えられた。
大会実行委員会が準備した聖餐式では、様々な工夫が凝らされていた。聖卓・パン・ぶどう酒・フロンタルなどすべてのものを携え、太鼓の音に先導されて入堂し、すべてを奉献として捧げた。パンは、実行委員が小麦粉と水と塩で焼いたものを用いた。分科会の中で分かち合ったことを、祈りにしてこの聖餐式に持ち寄った。また司式団には女性の司祭にあえて加わっていただき、日本聖公会総会が男性のみであった司祭職を女性にも公式に開いたことについて思いを深めた。説教は京都教区の小林聡執事。世界の様々な聖公会の教会とその活動を見てこられた後、日本に帰ってからジュビリー2000の活動に取り組んできたその経緯などについてお話をされた。
その他の礼拝も、テゼの歌を用いた祈りと黙想の集い、話題の「ゴスペル」を取り入れた音楽礼拝、開催地に程近い岡谷聖バルナバ教会(中部教区)の歴史について思い巡らす礼拝など、新たな試みが行われた。
アピールタイムでは、聖公会の青年たちの多様な働きを非常に具体的に感じることができた。地雷撤去、外国人医療、フィリピン自立支援、移住労働者の子どもへの教育活動、債務帳消しキャンペーン、聖公会生野センター、日韓交流プログラムなどなど。キャンプファイヤーでは、京都教区の青年たちを中心にパワーを爆発させた。もちろん毎晩夜を徹して交流が行われたことは言うまでもない。
全国青年大会は、大会そのものが目的なのではなく、あくまでも教会・教区での青年たちの働きの活性化に重点がある。参加した私たち一人一人のこれからの働きが問われることになる。そして、その働きこそが、この大会を支援してくださった全国の教会への最も大切な感謝の表現となるのでは、と考えている。
(全国青年大会実行委員長/矢萩新一さんから)
大韓聖公会の働き学び、今後の交流と学びを約束
日韓交流プログラム
8月16~22日ソウルにて、大韓聖公会韓日協同委員会と日本聖公会日韓協働委員会の主催で、第6回日韓聖公会青年交流プログラムが行われた。
今回はLabor Program(生活が困難である人々を支援している「分かち合いの家」の活動を支援する)、Spirituality Program(祈りを通して自分を知り、また相手を知ることで互いの感性を深める)、Visiting Program(開発の進んでいる地域とそうではない地域を訪れ、クリスチャンとして彼らとどのような関係を築いていくべきかを考える)、Making a Statement(この交流プログラムを通して、日韓の青年たちが二つの国の未来を見据えてこれからの決意と方向性について共同声明を作成する)というプログラム。
以下の聖公会の宣教施設を実際に見学した。
・移住労働者の生活支援センターである南楊州(ナムヤンジュ)教会のシャロームハウス
(ここでは見学と同時に施設補修ワークも行った)
・知的障害者のための施設である江華(カンファ)教会のウリマウルの村
・女性の高齢者施設である聖アンナの家
・国とソウル市に委託された野宿生活者支援施設である自由の家
(ここは食事、宿泊提供などで現在800人が利用可能。また病気治療、社会復帰の訓練なども企画されている。)
・ ソウル大聖堂の諸活動の見学や体験(野宿生活者や独居老人、欠食児童のための給食活動など)
また、フランシスカンの2人の神父の指導で祈りと賛美と粘土を用いて「私の神様」像を作り分かち合うというプログラムも行った。もちろん毎晩夜遅くまで交流。西大門刑務所跡、カンソンボ(江華島(カンファンド)事件)など日本による侵略の歴史的現場、景福宮、国立民俗博物館、ソウル市内見学などもあわせて行った。韓国語を理解しようとする日本人参加者が増えてきたこともあり、よい雰囲気の中での出会いとなった。また韓国の青年たちが弱い立場に置かれている人たちと共に生きようとして生まれている多くの活動にふれ、大いに学ばされた。今後の日韓の青年の交流を継続させると共に、これらの活動に触れた参加者が今後日本で何をしていくかも大きな課題である。
(横浜・千葉復活/東佳奈さんから)
聖公会日韓青年交流プログラム 声明文
私たちは2000年8月17日から、23日まで、韓国ソウルにて、お互いの違いを認めあい、これからの新しい関係を築くために聖公会日韓青年交流プログラムをおこないました。私たちは、このプログラムの中で私たちに限った交流に留まらず、社会の中で小さくされた人と、その人と共に働く人たちの活動を学びました。「ともに歩もうこの道を」というテーマのもと「この道とは何か」と考えてきました。今後も 「この道」を考えながら、私たちは主体になって交流を続けて新しい出会いを作り出します。
1.私たちはイエス・キリストの愛と正義のもとに お互いの社会的・歴史的真実を確認して、これからの私たちの関係を築いていくために、聖公会日韓青年交流プログラムを続けます。
2.わたしたちは 信仰的な交流を続けお互いに 言葉・文化・歴史・社会 を学びあい、1年に1度、日本と韓国から集まります。
以上の交流プログラムのため日本聖公会・大韓聖公会の協力を要請します。
2000年8月23日
2000年聖公会日韓国青年交流プログラム参加者一同
井戸端会議ホームページ
大阪教区の青年有志の会「井戸端会議」の掲示板が作成された。アドレスは次のとおり。http://tcup70.tripod.co.jp/7003/enfants.html
大阪でゴスペルを
大阪教区では月1回青年有志の集い「井戸端会議」を行っている。7月1日はそうめんを食べながら川柳を作るという企画。福音書を読み、それについて川柳を作り発表しあった。8月5日は約10名が集まり、映画「シュリ」を観、その後交流。朝鮮半島の統一についても考えた。9月4日、大阪教区から青年大会に参加した人の振り返りが行われ、約15名が参加。大会の感想、分科会の報告、大会聖餐式、テーマについてなどについて話し合った。その際に荒川真紀さん(聖パウロ)の以前からの提案もあり、10月22日の大阪教区礼拝で「ゴスペル」を歌いたいという話になり、合宿を計画した。
10月6~9日、大阪教区青年有志ゴスペル隊強化合宿実行委員会主催、大阪教区教務局後援により、大阪聖パウロ教会、大阪聖愛教会、大阪城南キリスト教会を会場に、ゴスペル強化合宿を行った。朝・昼・晩と練習時間を設け、1回の練習で発声から皆で合わせるまでのプロセスを盛り込み、1回でも練習に参加してもらえるよう工夫をした。練習を通じてお互いのことを知り合うきっかけともなった。ゴスペルは、抑圧の中にあった黒人たちによるダイナミックな歌である。大阪は、在日コリアンが多く生活しているが、こうした状況の中で、私たちはゴスペルをどう歌うか、ということも私たちの課題の一つだった。そこで、聖公会生野センターの呉光現(お・くぁんひょん)さんを招き、違いと差別という視点から在日朝鮮人、障害者について講演をしていただいた。また鈴木淳によるラップ講座も行った。
10月15日には、阪急梅田にて大阪教区青年有志ゴスペル隊で路上パフォーマンスを行った。そして10月22日の教区礼拝では、大阪教区の青年だけではなく、沖縄、京都、神戸教区の青年、他教派の青年、ゴスペルのワークショップに参加している方々と歌うことができ、感謝に満ちた一日となった。
今後も月1ペースで行われている井戸端会議を続ける予定である。また青年たちそれぞれのタレントを生かして授業を行う青年大学構想などもあり、今後の大阪教区の青年の動きが注目される。
(大阪・尼崎聖ステパノ/鈴木淳さんから)
神戸教区青年交流会のスキーキャンプ、来年二月一六日〔金〕~一八日〔日〕まで米子聖ニコラス教会にて。
神戸の交流会
9月9日、神戸聖ミカエル教会において、全国青年大会反省バーベキュー大会が行われ約10名が参加した。京都・大阪教区の青年も集まり、今回の大会で得たことをどのように自分の教会・教区に生かせるかなどについて話し合い、今後につながる非常に有意義なひとときであった。
また、9月16~17日、明石聖マリア・マグダレン教会にて神戸教区青年交流会秋のキャンプが行われた。初日は教会補修のワーク。次の日は聖餐式に参加。午後からは敬老会に出席して信徒の方との交わりの機会を持った。約25名が参加。なおキャンプ中に行ったテゼの歌を用いた礼拝で集められた献金は、東海集中豪雨でのボランティア活動を行っている神戸元気村に送られた。
(神戸・神戸聖ヨハネ/さこ田直文さんから)
韓国語教室、青年たちが始める
今年の日韓青年交流プログラムに参加した東京のメンバーが中心となり、韓国語教室を開講することになった。これは、韓国側参加者に日本語を話せる人が多くいたことにショックを受け、また日本語を話さない韓国の参加者ともっと話がしたいと考えたことがきっかけ。現在日本の大学院で学んでいるキム・フナさん(大韓聖公会ソウル大聖堂信徒)を講師に、10月23日から教室をスタートした。毎週月曜日午後7~9時。場所は東京聖三一教会。月謝は月5,000円。現在、受講生募集中。 (東京・池袋/河崎真理さんから)
青年大会後、東京で相次ぎ青年の集い
青年大会後、東京教区の中で、有志による様々なイベントが行われている。9月23日、東京教区フェスティバル終了後、池袋聖公会において、青年の集い(中高生を含む)を行った。内容は、名前ビンゴ大会、鉄板焼きをして語り合い。10月22日には、東京聖テモテ教会において、教会バザー終了後、バーベキューを行った。11月5日、大聖書展見学ツアー(中高生を含む)を行い、その後練馬聖ガブリエル教会で食事を共にした。11月12日には、中高生向けの運動会を企画。さらに11月23日にも青年の集いを行い、ボーリング、晩祷、ゴスペル演奏、落語、鍋会を行う予定。今年はこういった形で交流プログラムを中心に行い、来年から学習会やボランティア活動などを取り入れて具体的な活動を行っていきたいと考えている。
(東京・聖テモテ/大畑智さんから)
青年大会に向け、東京で
7月1日、三光教会にて「東京教区青年有志の集い」を行った。約10名が参加。根田栄子さん(同教会信徒)から、現代の教育についてお話を聞いた。子ども達は環境に大きな影響を受けており、子どもというよりまず大人たちの行動自体を考え直す必要があるのでは、などのお話を実体験を元にうかがった。今の教育の問題について、真剣に討議する機会となった。 (東京・三光/橋本周二郎さんから)
水害の中で…
中部教区長野伝道区の青年の有志たちは、名古屋の水害で被災された方々に何らかの形で支援ができないかと考え、ハンドメイドのクッキーを焼き、飯綱高原で行われた中部教区研修会、上田聖ミカエル及諸天使教会での長野伝道区合同礼拝において販売した。売り上げ金は、全額東海地区での集中豪雨で被災された方々への支援金として送った。 (中部・岡谷聖バルナバ/米山友美子さんから)
中部教区青年交流会から中部教区各教会に配信された公式報告
2000年9月16日
日本聖公会中部教区 各教会 聖職・信徒ご一同様
日本聖公会中部教区 青少年プログラム委員会
委員長 司祭 アシジのフランシス 西原廉太
ユースコーディネータ フランシス 宮島義人
中部教区青年交流会が、9月14日から16日まで、野尻湖YMCAキャンプ場にて行われました。
ご承知の通り、中部教区の中の一部地域が、今回の集中豪雨によって大きな被害を受けました。この事態を受け、主催側としては予定通り実施するかどうか、あるいはボランティアを組織することが可能かどうか、等の検討を直前まで行いましたが、最終的には交流会自体は予定通り実施し、その中でこのことを覚え、そういう状況の中でわたしたちが集まり、また集められていることを思いめぐらす機会ともしたいと願いました。
交流会参加予定であった青年のうち、3名は参加を取りやめて名古屋でボランティアに加わるという決断をしました。また、名古屋からの参加者は、集中豪雨による被害のために不足した車を調達するため、レンタカー探し等で出発が大幅に遅れ、午前2時にようやく到着しました。東京からの参加者も、上信越道の一部区間が不通になっており、中央道への迂回を余儀なくされたために到着がやはり遅れました。交流会の始まりからして、すでに名古屋で起きた出来事と決して無関係には行うことができないということを参加者一同実感しました。
1日目の夜、この出来事をどのように参加者の中で分かち合うことができるかについて、深夜までスタッフは協議を重ねました。結果的には、交流会のプログラムを一部変更することにし、キャンプファイヤーを予定していたところで、名古屋の出来事を覚えるカウンシルファイヤーを行いました。
カウンシルファイヤーでは、まず名古屋でボランティアに加わった3人の青年のことを覚えました。そして、神戸その他から名古屋に来てボランティアをしている青年たちの活動が紹介されました。その後、名古屋から参加した甲村僚章さんと佐藤泉さんから、自分たちが直接体験した今回の水害についての状況と思いを聞きました。加えて、川村直子さんと市原信太郎さんからもそれぞれの体験の分かち合いがなされ、別の視点が与えられました。
最終日、聖餐式の中で、名古屋でボランティアをしている青年から送られたリポートが分かち合われました。また、信施は支援金として活動のために用いるという意図を持って捧げられました。そして、ボランティアを希望する青年には活動に関する諸情報が提供され、何人かの青年は交流会終了後活動に加わる予定です。
今回の交流会には、愛岐・長野・新潟伝道区から、また東京から、他教派からも三十人ほどの参加者があり、充実したプログラムを行うことができました。交流会を実施したことにより、多くの青年が一つに集められ、お互いが顔と顔を合わせて語り合い、祈りの生活を共にする中で、隣人の存在に気づかされ、名古屋で起きた出来事と自分たち一人一人の物語とがつながりを持った出来事なのだということが実感されました。今回の交流会実施にあたり、祈りと励ましを頂いたすべての方々に、心から感謝とお礼を申し上げます。今後とも、青年たちの歩みをどうぞお支えください。
7月20~27日、九十九里ホームにて、横浜教区の青年活動の一環として、青年たちが自ら企画したボランティア・キャンプが行われた。約10名が参加。今回は、ディサービス、特別養護老人ホームでのワークのほか、身体障害者養護施設(聖マーガレットホーム)も訪問し、利用者とのふれあいのときを持つことができた。これからこのプログラムの参加対象を高校生にも広げていきたいと考えており、今後の展開が期待される。(横浜・川崎聖パウロ/小林祐二司祭から)
8月30日~9月3日、昨年に引き続き、藤沢聖マルコ教会青年会が主催して、沖縄への旅が開催され、約15名が参加した。今回は、首里城、平和祈念公園、普天間基地、嘉手納基地、辺野古(海上ヘリポート基地建設予定地)、愛楽園、万座毛、琉球村などを訪れ、沖縄で起きている「日本」の問題や沖縄の文化などについて学びを深めた。
(横浜・藤沢聖マルコ/渡部明央さんから)
東京で青年大会のリユニオン
9月30日、東京教区三光教会において、全国青年大会全国青年大会リユニオンIN関東が、大会参加者有志の企画で行われ、約30名が参加し、青年大会についての感想を分かち合った。当日は、焼きそば・お好み焼きを楽しみつつ、様々な意見を交換した。
(東京・神愛/森正道さんから)
聖公会の青年たちが翻訳し、出版
聖公会青年MLで翻訳が呼びかけられたCCA-YOUTHの聖書研究ワークショップ「アジアの視点で聖書を読む」1998年の報告書の翻訳本が、赤堀牧さん、市原信太郎さん、蛭子慶太さん、川村直子さん、神崎直子さん、村瀬義史さん、藤本実千代さんらの翻訳で完成し、販売されている。内容は、同会議の報告や礼拝式文などに始まり、アジアで疎外されている人々の視点から聖書を読むことで、イエスと教会の宣教のとらえなおしをした発題や、アジア各国のレポートが多数掲載されている。一部400円。お求めは青年ネット事務局まで。なお、この翻訳本はキリスト教アジア資料センターの『アジア通信』(2000年10月号)でも推薦図書として紹介された。 (全国ネット事務局)
CCA、新体制でスタート
CCA(アジアキリスト教協議会)第11回総会が6月1~6日、インドネシアで開催された。今総会ではCCAの組織再編が行われた。最も重要なプログラムエリアも3つのセクションに再編され、青年委員会はエキュメニカルフォーメーション・ジェンダー・青年セクションに含まれることになった。なお、プログラムセクションごとに各国から1名ずつ委員が選出されているが、このセクションには日本から相原が選出された。 (全国ネット事務局)
エキュメニカル学生青年運動の今後に向けて
第2回学生青年運動エキュメニカル協議会が11月2~4日、御殿場東山荘で開催された。主催は、NCC青年委員会、日本YMCA同盟学生部委員会、SCM協力委員会。聖公会からは、管区学生青年運動協力委員会からの要請で、東佳奈さん、大畑智さん、小林聡執事、西原廉太司祭、黒田裕司祭、川村直子さん、村田真さん、野村潔司祭、相原が参加。その他、YMCA、カトリック、在日大韓、ルーテル、日本基督教団、バプテスト連盟、NCC、KCC、NCC関西青年協議会、仙台学生センター、神戸学生青年センター、北海道クリスチャンセンター、SCFなど、約40名の参加。CCA-youthの青年担当幹事も参加した。
目的は、1997年に開かれた第一回協議会と、その後のエキュメニカルな運動の成果をふまえ、各教派・団体における運動の取り組みについての情報と経験を共有し、現代日本社会におけるエキュメニカル学生青年運動の役割と可能性を模索するというもの。
内容は、開会礼拝の後、まず発題。エキュメニカル・ユース・フォーラム関東、Asia Students and Youth Gathering、バザール・カフェ、SCM現場研修、CCAについて。次の日は、李鍾元さん(立教大法学部教授、国際政治学者)による主題講演。韓国民主化闘争におけるキリスト者青年たちの取り組み、その中での自分の経験、現在の民主化闘争後のアジアの状況において、私たち目指すべき方向性について語っていただいた。
その後分団に分かれ、今後の私たちの取り組みについて協議した。その中で、まず、MLなどでエキュメニカルに情報交換を恒常的に行うこと、地域のネットワークを作る努力をすること、それぞれで取り組んでいる課題を共有化し協力の可能性を探ること、エキュメニカルにリーダーシップトレーニングを行うこと、アジアレベルの運動と連携していくことなどを、全体セッションで確認しあい、エキュメニカルな「感謝の礼拝」をおこない、閉会した。
アジアの多くの国は、軍事独裁政権に対する民主化闘争の中で、キリスト者の青年たちが大きな活躍をし、民主化後もグローバリゼーションによる経済侵略による貧困の中にあり、そうした状況の中で青年たちはヴィジョンを見、そのためにすべきことを感じ取り、活動している。貧困・環境破壊を作り出している側の日本では、そうした現実が自分のこととして感じにくいという特殊な状況にあり、その意味で新しい世界へのヴィジョンが生まれず、こうしたことがヴィジョンに向かう学生青年活動の活性化を困難にしている一つの要因であるのではないだろうか。したがって、今私たちがどこに立っているのかを理解する視座とヴィジョンを養うためのトレーニングプログラムが不可欠であろう。 (全国ネット/相原)
京都教区夏の活動報告会
11月3~4日、奈良基督教会において、京都教区宣教局教育部青年活動窓口の主催で、京都教区夏の活動報告会が行われ、東京・横浜・大阪教区の青年を含め約25名が参加した。違う形で活動している青年同士が情報を交換した。全国青年大会の11の分科会や、夏の小中高キャンプなど、2日間かけてたっぷりとお互いの報告を聞いた。
(京都・大津聖マリア/前田敏宏さんから)
京都のニュースレター
京都教区青年「まったり元気」計画推進実行委員会の発行による、京都の青年向けのニュースレター「Face to Face」が7月25日に発行された。内容は、編集長の藤原健久司祭(教区宣教局教育部青年活動窓口担当)の挨拶。2月におこなわれた寄せ集めの会の報告とゲームの寄せ集めについて西井智子さん(アグネス)、5月の交流キャンプの報告を斉藤仁さん(京都聖マリア)、京都聖ステパノ教会の壁画(ブロック塀)について小林聡執事(京都聖ステパノ)、音楽会について浦地愛さん(京都聖マリア)、仕事である児童館について竹村紀美香さん(奈良基督)、青年の集まりについて野崎裕輝子さん(京都聖マリア)。キリスト教との出会いについて服部樹美さん(奈良基督)などなど。第2号は「夏の活動報告会」についてまとめたものを近日中に発行する予定。
(西井智子)
九州教区の青年たちが中心となって実行委員会を組み「第2回九州教区平和を考えるプログラム“長崎に立つ”永井博士の信仰にふれる -如己愛人-」を来年2月10~12日、長崎で行う。なお、第1回の報告書がすでに完成している。(九州・宗像聖パウロ/柴本孝夫司祭から)
どうなる、管区機構
5月23~25日に行われた日本聖公会第52(定期)総会において、「日本聖公会管区機構試行に関する件」が可決された。議案可決により、現行の委員会は、機構改革検討委員会報告による新基準に沿って2000年末に見直されることになった。同委員会の報告によれば、学生青年運動協力委員会は「特別委員会」に含まれ、2000年末に終了し、その役割を管区担当主事に引き継ぐとしている。仮に委員会を設置する場合はあらためて期限付きの特別委員会として設置すべしとのこと。
学生青年運動協力委員会は1962年に設置され、これまで日本聖公会に多くの人材を生み出してきた。そして、1992年には全国青年大会を仕掛け、現在の青年運動の活性化の基礎を作っており、青年大会もこのニュースも、協力委員会の働きなしには成り立たない。しかし今回の決議により協力委員会は今年末に終了となる。
現在、管区主事会において、現行委員会から意見を求めつつ、新体制を検討している。人材育成という一点だけを考えてみても、これまでの協力委員会の働きはきわめて重要であり、そのことを十分踏まえた上で新しい体制を作るべきであろう。今後の管区の組織改革の動きに注目していきたい。 (全国ネット/相原)
京都・大阪・神戸
合同サッカー大会
11月23日(木)、大阪府三島郡島本町の淀川河川敷において、京都・大阪・神戸の青年たちによる合同サッカー大会が開催される。数年前から行われているが、今回は、神戸教区が大量参加した青年大会後の合同大会であり、盛り上がりが期待される。(京都・奈良基督/当舎真さんから)
北海道から
北海道教区で今年行われた二つのイベント「夏ひろば―恵み・賛美・交わり―」と「ミレニアム・フェスティバル」では、青年たちが様々な場面で活躍した。特に「夏ひろば」のほうではアンダー40の集いを行った。集いの中で、沖縄スタディツアーなどの企画も出され、今後の動きに注目。
(北海道・札幌キリスト/下沢昌司祭から)
エキュメニカルなクリスマス
12月17日、札幌市内のカトリック、教団、聖公会の青年による合同クリスマス会が計画されている。聖公会の青年たちも企画に参加し、会場は札幌キリスト教会(聖公会)になる見込み。
(北海道・札幌キリスト/下沢昌司祭から)
ヒューマンチェーンに参加
1998年夏に開催された「日米聖公会青年平和と和解への旅」参加者有志が、沖縄サミットにあわせて行われた「基地はいらない人間の鎖県民大行動」への参加を、日本聖公会の青年たちにメール等で呼びかけ、沖縄教区の青年を中心に7月20日の嘉手納基地包囲行動に参加した。 (東京・神愛/吉岡京子さんから)