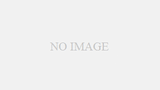かつて nskk.org に掲載してあった全国青年ネットワークニュースをarchive.orgより復刻しました。
全国青年ネットワークニュースのプリントを探しています。
第1号から9号のプリントや本文テキストも探しています。
お持ちの方はご連絡ください。
18号 2002年5月28日発行
今夏、聖公会青年のためのリーダーシップトレーニング開催
八月九日から一三日迄、長野で、日本聖公会の全国の青年を対象とした、リーダーシップ養成のプログラムが、管区青年委員会と当ネットワーク事務局の主催で開催される。国際協力NGOなどの間でワークショップファシリテーターとして有名な池住義憲氏や立教大学助教授の西原廉太司祭を講師に迎え、五日間の学びと交わりの時を持つ。
一九九二年に日本聖公会全国青年大会が開催されて以降、全国の青年たちの活動が活性化し、現在では全国各地で様々なプログラムが行われている。そうした中で、「青年たちで集まったはいいが、何をしたらいいんだろう」というように、プログラムの内容的な充実をめざす声が青年たちから聞かれるようになってきている。
そこで、青年委員会(旧学生青年運動協力委員会)と青年ネットワーク事務局では、一年かけて青年大会とは別の新たなプログラムを検討を重ね、開催することになったのが、このリーダーシップ養成のプログラムである。
五日間の研修では、何かの集いの際に用いることができる実践的な方法を楽しく学びつつ、そこからリーダーシップのあり方を学べるような構成である。リーダーシップの取り方や、さらには教会も含めて既成組織のあり方そのものが世界的に大きく見直され、変化しており、そうしたことをふまえたものとなっている。また単にそうした技術的なことを学ぶのではなく、世界、そしてキリスト教に自分自身がどう向き合っていくかをあらためて見つめることがこのプログラムの基底になっているのが最大の特徴であろう。
全体のファシリテーター(進行促進役)には、元アジア保健研修所事務局長で、現在は大学やNGO、国際機関などでファシリテーターとして活躍している池住義憲さん(聖公会信徒)。講師には、立教大学助教授、聖公会神学院兼任講師、NCC(日本キリスト教協議会)書記でもある西原廉太司祭。
全教区から各二名程度、できるだけ均等に参加者が集まることができるよう、申込は、各教区のキーパーソンにするようになっている。
詳しくは、青年ネットワーク事務局まで。
北関東教区で青年の集い
昨年十二月、志木聖母教会の青年を中心に、青年会活動への声が高まり、管理牧師である教区主教に相談すると、喜んで賛成してくださり、「有志による青年会」が発足しました。
さっそく十二月二九日に、「青年の集い」を開きました。ほとんどネットワークもないのに、十名の青年が集まりました。会では各教会の青年の現状などを語り合い、親睦を深めました。
それから二週間後には、早くも二回目の「青年の集い」を一月十四日、浦和の教会で開きました。十名が参加。青年で集まって「何をしていこう」ということについて考え、話し合いました。教会から怒られるのを恐れずに、何でもやってみよう、思いついたことから取りかかろう、できることから継続した活動をしていこう、という意見が出されました。
二月十一日には志木の教会で三回目の青年の集まりを開きました。六名が参加。このときは、「自分のタレントで青年会とかかわってください」というテーマで語り合いました。教会とどうかかわっていいか分からない、教会に居場所がないとの青年たちの声がある中で、むしろ、教会に自分を合わせようとするのではなくて、自分のタレントを積極的に出して教会にかかわっていければ、と話しました。その後、居酒屋で交流会。
また、この青年会活動と並行して、インターネット上でのメール配信をする「北関東青年ネットワーク」も開設しました。
この集まりを通して、青年たちの交流が生まれ、教会の中で青年たちが楽しく過ごせたらイイなと思っています。
(北関東教区・志木聖母教会/川澄幸宏)
日韓交流、今年は韓国で開催
毎年、韓国と日本が交互に会場となって行われる日韓青年交流プログラム。今年の開催地は、韓国。日程は八月一四~一九日(予定)で、現在調整中。
アフガニスタン難民レポート
昨年の九・一一事件後、アメリカはアフガニスタンに大規模な攻撃をしました。そのアフガニスタンの難民キャンプの調査を行った石橋聖トマス教会の川嵜美智子さんが聖公会新聞一月号に寄稿したレポートを転載します。川嵜さんは現在テヘラン(イラン)でペルシア語を学びつつ難民に関するフィールドワークを行っており、その後、難民学研究所のあるトロントに留学する予定。
九月一一日の同時多発テロ事件以降、パキスタンのアフガン難民キャンプでは変化が起こっている。アフガン難民は主として三世代に区分される。ソ連侵攻と共に逃れ出てきた第一世代、その後激化する内戦からアフガニスタンを後にした第二世代、そして第一・第二世代の子供たち、つまり難民キャンプで生まれ育ち祖国アフガニスタンを知らない第三世代だ。今、アメリカの同時多発テロ事件、そしてそれに続く空爆から逃れて、新たに難民となった人々が日々パキスタンにやって来ている。いわば第四世代ともいえる彼らは、今までのアフガン難民以上に、憎しみ・怒り・絶望など、大きな傷を心に抱えている。
大地に突き立てた棒に、ボロボロの布を引っかけただけのテント。吹きさらしで、防寒具はおろか地面を覆う敷物すらない。それが彼ら、第四世代の人々の住居だ。彼らの多くは国境で賄賂を支払い、パキスタンに密入国してくるため、難民キャンプに辿り着くころには全ての財産を使い果たしている。当然、不法入国・不法滞在となるため、難民登録もできず、同時にあらゆる機関から支給される援助物資を受け取ることができない。また、彼らの多くは密入国が当局に知られるのを恐れ、既存の難民キャンプに隠れ住んでいるため、NGOは勿論、UNHCRさえも彼らの生活実態はおろか、存在すら把握できていないのだ。彼らは既存の難民キャンプに以前から住む知人や同族を頼り、国境を越えてやってくるのだが、期待していたような援助はなく、食料や水さえも同族から僅かに分けてもらい日々食いつないでいる状態だ。
空爆による被害は絶大なものである。一方的に、ただ上空から逃れようのない、反撃しようのない形で爆撃するのは、もはや戦争ですらない。テロとは無関係の一般市民が、多数犠牲になっているのはご承知のことと思う。十歳にも満たない子供達が、本物の銃を握りしめて「アメリカに死を!」と叫ぶ姿を何度も見かけた。彼らの瞳は、父を母を兄弟を友人を同胞を、仲間を殺された怒りに燃えている。憎しみからは憎しみしか生まれない。空爆や他国に後押しされた戦争からは、第二・第三のテロリストを生むだけだ。
空爆が終わっても、表面上戦争が解決しても、人々の生活状態は変わらない。マスコミがアフガニスタンを取り上げなくなって、日々のニュースから難民キャンプや空爆の映像が消えても、日本と同じアジアの一角に生きる手段すら取り上げられた人々が、過酷な生活に耐えて生きていることを忘れないでいただきたい。
(大阪教区・石橋聖トマス教会/川嵜美智子)
神戸教区青年交流会
□スキーキャンプ
二月八~十日、米子聖ニコラス教会をベースにして、ここ数年恒例となっている大山スキーキャンプが開催。今年は三年目で、参加者の腕前も上がってきた。またスキーのインストラクターの資格を持つ神戸聖ペテロ教会信徒の萩原氏から指導を受けることができた。夜はこれまた恒例の皆生温泉に浸かり疲れを癒し、山陰名物の蟹鍋に舌鼓を打った。このプログラムは今後も継続してゆく予定である。
(報告 神戸教区青年交流会広報)
□神戸伝道区青年会主催 大斎集会
三月十六日、神戸聖ヨハネ教会にて姫路顕栄教会牧師、藤井尚人司祭を講師に招き、テゼの形式を元にした大斎集会が行われた。参加者は十名。内容は主に歌と黙想であったが、藤井司祭の絶妙な指導のもと、非常に有意義かつ充実した時間を過ごした。
(報告 神戸聖ヨハネ教会 さこ田直文)
□神戸伝道区青年会新人歓迎BBQ
四月二十一日、夕の礼拝後、神戸教区会館で行われた。参加者は近隣の教会の牧師家族を含め約四十人。また教区青年交流会チャプレン瀬山公一司祭の明石転勤に伴い、その歓迎会も同時に行われた。
(報告 神戸聖ヨハネ教会 さこ田直文)
□執事按手式・大礼拝
四月二十九日、神戸聖ミカエル教会にて、神戸教区執事按手式・教区大礼拝が開催され、中原康貴・坪井智、両新執事が誕生した。当日は、先の芸予地震によって大きな被害を受けた松山聖アンデレ教会牧師館改築のためのバザーが行われ、青年交流会はビールを販売。売り上げを全額松山へ献金した。また同時にこういった行事には恒例となっている青年交流会で調理・準備した豚汁が参加してくださった方々から好評を得た。
(報告 神戸教区青年交流会広報)
□ワークキャンプin ミカエル教会
三年ぶりに、神戸聖ミカエル教会を会場にしてのワークキャンプが五月三~五に開催された。教会北側の歩道橋に大きく伸び出した杉の枝の伐採、庭の木々の剪定、池の掃除など。参加者はのべ約二十人ほど。夜の親睦会、またワークが終わった瞬間に雨が降り出すなど天候にも恵まれ、今年一発目のワークは有意義なひとときであった。
なお、本キャンプで中村香さんが教区青年交流会代表を辞任し、新たに神戸聖ヨハネ教会の水野宏明さんが代表に就任した。
神戸教区青年交流会の情報はHPにて(全国青年ネットワークからリンク)ご覧下さい。
(報告 神戸教区青年交流会広報)
大阪の青年礼拝
十二月十六日、大阪教区の第3回青年礼拝を行いました。この回は、クリスマス礼拝と称して、夕の礼拝に沿いつつ、ページェントをメインに静かな礼拝を行うことが出来ました。青年が脚本を書いたクリスマス物語のページェントを、青年で演じました。マリアやヨセフなど、登場人物の心の動きに注目し、イエスさまが生まれるまでの受胎告知のシーンや、ヨセフがマリアと縁を切ろうと思い悩むシーンに特に注目してシナリオが作成されました。
なぜ、マリアのもとであったのか、マリアは迷うことなく「お言葉どおり・・・・」という言葉が言えたのか?ヨセフは苦しまなかったのか?
たくさんの疑問が浮かび上がり、聖書が意味することは何だったのか?私達には随分と難しかったのですが、私達なりにクリスマスとは何なのかを話し合い、考え、勉強したとき、私たちはただお祭りのようなものとしてしかクリスマスを迎えていなかったのではないか、と考えました。クリスマスを迎えるにあたり、クリスマスとは?ということを共に考える良い時間になったのではないかと思っています。
その後は大阪教区の青年特製のおでんをみんなで食べながらの楽しい交流会となりました。青年たち自身の働きや、各教会の働きなどを知ることができ、とても有意義な時間を持つことができました。
当日は、約二十名ほどの方が礼拝に出席してくだいました。神戸教区や京都教区の青年もきてくださいました。
一月二六~二七日の四回目の青年礼拝では、石橋聖トマス教会にて、新年ワークキャンプを行いました。その内容は、収益を全てアフガン難民への献金とするチャリティクッキー作りと青年の交流、そして、今後の青年の活動についての話し合いでした。アフガン難民キャンプでは、空爆以後難民の数が増え続けています。その過酷な状況の中にある人々のために、私たちに何かできないのだろうかと、青年たちで話し合い、その結果、みんなでクッキーを作って、販売し、その収益をアフガン難民キャンプを支援する団体に献金してはどうか、ということで実現しました。
さらに四月十四日には、大阪聖パウロ教会で、五回目の青年礼拝が行われました。または五月十二日に六回目の青年礼拝を行いました。
この青年礼拝・青年の集いが、確実に根付き、教区の青年の拠り所とすることが出来るように、焦らず、じっくりやってまいりたいと思います。
(大阪教区・石橋聖トマス教会/村上恵依子)
リーダー研修会
五月三・四日、京都教区の青年有志によって「リーダー研修会」が大津聖マリア教会にて行われました。二十名ほどの参加があり、「京都教区教育部キャンプとは」という話し合いがもたれました。ブレインストーミングでキャンプのキーワードを出し合い、六つの項目に絞っててグラフを作り、自分たちの適性を試し、教育部長と宣教局長の話を聞きました。夏に行われる小・中・高生のキャンプに向け、スタッフの意識を高めようと企画されたものでした。
(京都教区・上野聖ヨハネ教会 矢萩新一)
よせあつめの会
三月三~四日、大津聖マリア教会で京都教区青年による「よせあつめの会」を行いました。今回でこの企画は二回目。参加者は、二十七名。「出会いたい・熱く語ってみたい・自分を見つけてみたい」がキーワード。他者が見た自分を知ることで自分を見つめ直し、人の見方や考え方に気付き、それらを比較したり、理想などを自由に話し合ったりしました。これからもこんな感じの青年活動を続けていきたいものです。(京都教区・大津聖マリア教会/藤本仁)
ピースツリープロジェクト
九月十一日後、ある青年とのやり取りの中で、共に祈ることの必要を感じさせられ、青年、子供など数人と、事件の数日後に祈りの時を持つことが出来た。その後、ステパノ教会に出入りしている様々な人たちと「平和宣言一〇・二一」を作った。作成に青年達が積極的に関わってくれた。
昨年の降臨節には教会前に、平和への願いを込めたメッセージカードやオーナメントを飾り付けたクリスマスツリー「ピース・ツリー」が設けられ、一月六日顕現日まで設置された。高さ二・一メートルのツリーに飾り付けられたカードには「早く平和な世界に戻って」「アフガンの子供達が幸せになりますように」等と小学生や親子連れから寄せられた百以上のメッセージがずらり。府内外や外国からもリースやオーナメントが届いた。平和な世界の実現を町の人々と願うことが出来た。この企画は、私が、若い人たち中心の市民ネットワーク「CHANCE!~平和を創る人々のネットワーク~」に参加したことがきっかけで、そこで知り合った人達がピース・ツリー作りを発案した。
教会では様々な人々が賜物を出して下さった。ツリーをプレゼントしてくれる人、設置や飾り付け、オーナメント作り等を指導してくれる人等など。日本各地、時には韓国からわざわざオーナメントを届けて下さる方もあり、訪れてくれた人々とも交わりが出来た。この動きにステパノの青年も加わり、またクリスチャンではない青年達が、熱心に動いておられるのに接し多くの感動が与えられた。
(京都聖ステパノ教会/小林聡)
東京で報告会
四月二十八日、在日大韓基督教会東京教会で、二月の終わりに九州で行われた、日韓在日共同プログラムの報告会が行われました。九州のホームレス問題を通して、日本のホームレス問題を考えたり、在日の問題について考えてみたり、炭鉱での強制労働について学んだりしました。また、去年一年間の歴史教科書問題を考えるエキュメニカルキリスト青年の会の活動報告と今後の方向性について話し合いました。その後交流会を開催。主催はNCCYと全協で、参加者は聖公会の青年も含めおよそ二十名。
五月六日には、SCF(東京/中野)で、三月に行われたエキュメニカルユースイベントの報告会を行いました。何をやってきたのかを、実際に少しでも体験していただけるよう、イベントの中で行ったワークショップをいくつかやりました。その他、礼拝、交流会を行いました。参加者は約三十名。主催はNCC青年委員会。今後月一回程度で教派間の学びと交流の機会を持ちます。初回は六月三日を予定しています。
(東京教区・聖アンデレ教会/大畑智)
エキュメニカル青年の学習会
十二月十八日神田キリスト教会で、「山谷」(東京最大の寄せ場)についての学習会をしました。主催は、「歴史教科書問題を考えるエキュメニカルキリスト青年の会」。「歴史教科書問題」を教派を越えて捉えていこうという趣旨ではじまった会です。現在は、そのつながりを大切に様々な問題に取り組んでいこうとしています。
この学習会は、二月に行われたEYCK(韓国基督教青年協議会)、NCCY 全協(在日大韓基督教会の全国青年会)主催の共同研修プログラムの準備会を兼ねたものです。そのプログラムをより実りのあるものとするために、自分たちの住む場である東京の寄せ場の状況を知っておこうということで、今回の学習会が企画されました。山谷の歴史や、山谷でのキリスト教の働きなどについて学びました。(京都教区 上野聖ヨハネ教会 矢萩新一)
アジアユースウィークの準備のためのワークショップが五月二十四~三十一日、フィリピンで開催され、東北アジア地域からは日本聖公会の米山友美子さん(中部教区/岡谷聖バルナバ)が参加する。
エキュメニカルユースイベント
三月二一~二四日、東京都日野市にあるラ・サール研修所において、日本リスト教協議会青年委員会主催のもと、第一回エキュメニカルユースイベントが開催されました。テーマは「和して同ぜず」。開催趣旨としては、全国のエキュメニカル青年運動のネットワーク化、次世代のリーダーシップの育成・強化。また、キリスト教青年の生き方の違いを共有し、社会の平和、解放を求める共同体のビジョンを生み出していくことです。十教派・団体から三十四人が参加しました。内容的には、様々な宗派による礼拝・祈りと黙想の集い、エキュメニカル運動から与えられた恵みについての青年による発題、池住義憲さん(聖公会)を講師に迎えたワークショップ、イエス劇発表等がありました。発題した村瀬義史さん(日本基督教団)は「本当に違いを大切にすること、多様性の中で生きることは簡単ではない。しかし、エキュメニズムとは、自分が安住している場から、自分が相対化され、挑戦されるような場に出てゆくこと。そのような場においてこそ、わたしたちはますます自分や他者を見出し、また、共に生きることへの希望を見出せるのではないか」と語りました。
四日間の中で、様々なプログラムの中で学び、また様々な教派の青年と出会い、その思いを分かち合う時を持つことができました。 (東京教区・池袋聖公会 加藤篤史)
SCM現場研修
三月九~一七日、大阪の生野と釜ヶ崎にて第二十四回SCM現場研修「差別の社会構造と私たち」が行われた。聖公会からは七名の青年が参加した。
初日は全員が、研修の拠点となる在日韓国キリスト教会館に集って交流し、これからの一週間を思い、改めて気持ちを引き締めた。二日目から釜ヶ崎研修生が「旅路の里」へと移動し、生野・釜ヶ崎に分かれての研修がスタートした。生野研修生は、日中は在日韓国・朝鮮人の人が経営する工場などで働き、夜は講演を聞き分かち合いの時を持った。釜ヶ崎研修生は、全員で支援団体の方のお話を聞いたり、炊き出し・夜まわりに参加したりする一方、多くの時間を各自でプランを立て自由に行動した。そしてこちらでも、毎晩分かち合いの時を持った。最終日には、また生野に集合し、一週間を振り返った。
私は、まず今の日本の社会構造において、野宿せざるを得ない状況に陥る人が出ることは必然であろうという事実に絶望感を覚えた。そして、そうだとすれば尚、行政・民間が力を合わせて受け皿を整えることが早急に求められると感じた。
そのためには野宿労働者に対する「差別意識」をなくすことがまず第一である。差別意識とは、野宿している人を異質なものとして捉え、いわゆる一般の人たちより下に見る見方であり、そのことに大きな問題があるのだと思う。そういう意識があるから、一人一人を人間として対等に扱うという、当たり前のことができなくなってしまうのだろう。
現場研修での一週間は、ほんのきっかけにすぎない。全てはこれからにかかっている。きっと今頃、みんな自分の場所に戻って、それぞれの形で関わりを進めているのだろう。(大阪・芦屋聖マルコ教会/錦織恵里)
在日・日・韓キリスト青年共同研修プログラム
二月二〇~二六日、在日大韓基督教会青年会全国協議会・日本キリスト教協議会関西青年協議会・韓国基督青年協議会と長い名前の三者の合同研修プログラムが、北九州の八幡聖オーガスチン教会を拠点に行われ、聖公会青年四名を含め、約五〇名が参加した。
研修の前半はNPO法人北九州ホームレス支援機構の協力を得て自立支援住宅の訪問、小倉のフィールドワーク、炊き出しの手伝い、パトロールなどを行った。後半は、戦時中に行われた強制連行に関する歴史フィールドワーク、というプログラム内容。
自立支援住宅訪問では、今そこに住んでいるおじさん達とはもちろん、生活保護を受けそこを出て新しく生活しているおじさん達とも話をすることができた。炊き出しの日は、弁当配ったり服を配る前の一時間ぐらいを使い参加団体三者が、それぞれ歌や踊りやマジックまがいみたいなのをやって楽しんでもらった。その後のパトロールでは、車で段ボールの家に突っ込んでくる襲撃事件も増えてきているという話を聞いたりした。前半のまとめとして寸劇を通じてグループごとに発表するという時間もあった。
後半の歴史フィールドワークでは炭坑労働犠牲者の遺骨が納められている納骨堂(永生園)、碑銘も没年月日も年令も彫られていないボタだけが、所狭しと目印のためおかれてあるだけの日向墓地(筑豊の田川)に行った。そこに集まっている人たちは韓国、在日、日本の青年という立場は違ったが涙が溢れてくるのはみんな同じだった。
今回のプログラム準備のため九州ではいろんな教派の青年が集まってミーティングを何度も行った。九州でそういう集まりが行われるのは珍しく、いいきっかけになった。山本尚生(九州教区・久留米聖公教会)
札幌での試み
二年前、聖公会の教会を会場に札幌市内超教派の青年クリスマス会が始まった。その後クリスマスだけ集まるのではなくもっとやろうということになった。取りあえず、ホームページを立ち上げ、メーリングリストを開始。そして四月にカトリック教会を会場に、「なんでこんなに教派があるの?」という学習会を行った。参加教会はルーテル、聖公会、カトリック、教団など。真面目なんだか不真面目なんだか、よく分からない集まりである。教派によってやたらに酒を飲みたがる人々、いつもシブイ顔をしている人々、とにかく社会的責任が気になっている人々、礼拝がしたい人々、ただ漠然と参加している人々など、いろいろいるのが面白い。また、内容によって、参加する教派別の出席者数にムラがあるのも面白い。こういう集いが全国的に広がっていくといいと思う。(札幌キリスト教会・下沢昌)
九州・山口のエキュメニカルイベント
四月二十九日、日本聖公会福岡教会で、同イベントが行われました。簡単なゲームをした後、NCCY、EYCK、全協、WCFなど各団体の活動、課題について報告がありました。その後ディスカッション、交流会。
今後定期的にこうした集まりをしていく他、夏の修養会などへの相互参加、合同礼拝、NCCYのプログラムへの参加、社会的な問題への取り組み、交流会の計画などについて話し合った。まずは情報のやりとりをということで、早速メーリングリストを作り、少しずつですがコミュニケーションをはかっています。(福岡教会/鶴沢礼実)