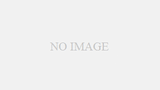かつて nskk.org に掲載してあった全国青年ネットワークニュースをarchive.orgより復刻しました。
全国青年ネットワークニュースのプリントを探しています。
第1号から9号のプリントや本文テキストも探しています。
お持ちの方はご連絡ください。
第19号 2002年11月23日
聖公会青年リーダーシップトレーニング開催される
八月九日から一三日、長野県飯綱高原ホテルアルカディアにおいて、二〇〇二ユースリーダーシップトレーニングが行われました。四泊五日で、日頃教会の青年活動などに携わる中でぶつかる様々な疑問や、青年活動におけるコーディネーターの役割、また、わかるようでわからないキリスト教や聖公会について共に学び考えよう、という目的で企画されたものです。それぞれの場で異なった体験をしてきた人々が集い、プログラムを通して考え、語り合うことで、とても濃い時間を過ごすことができました。
【一日目】ファシリテーターの池住義憲さんから、「アイスブレーキングの方法とその考え方」を学びました。ゲームを通して実際に、身を持って学びました。ゲームを楽しんでいるうちにすっかり緊張が解けました。アイスブレーキングが単にリラックスするためのものではなく、プログラム全体の意図を丁寧に反映させたものであるべきことも学びました。
【二日目】西原廉太司祭による「知ろう!学ぼう!キリスト教」。午前中は、出エジプト記のモーセの召命の箇所を中心に読み、聖書と私たち自身との関わりについて学びました。五、六人のグループに分かれてそれぞれ思ったことや疑問などを話し合ったのですが、同じ聖書の箇所を読んでいるのに、読み手によって着眼点が違ったり、気付くことが異なっていたのが興味深かったです。textとcontextとの出会いによってはじめて意味が生まれるのだということ、つまり聖書を読むということに「正解」はないのだということを学びました。また、新約・旧約を通して書かれている、「神の名を賛美すること」と「自己の存在を主張すること」が表裏一体であるということや、私たちの所属する聖公会についても、分かりやすく教えていただきました。初めて知ることがあまりにも多く、これまで自分がいかに知らなかったかを痛感しましたが、改めて「聖書ってすごい!」と思えたプログラムでした。
【三日目】日曜日は午前中、聖餐式。お昼ご飯は信州蕎麦を食べに行き、午後からは後半のプログラムの要となった「ロメロ」という映画を観ました。「ロメロ」はエルサルバドルで行われた民衆への弾圧に抗議し、暗殺されたロメロ大司教のことを描いた、事実に基づいてつくられた映画です。映画鑑賞後、数人のグループに分かれて感じたことなどを分かち合いました。
【四日目】「私たちと世界をめぐるワークショップ」。今のこの社会の中で、なくしたいもの・取り去りたいものは何?という問いかけをもとにワークショップを行いました。始めにブレインストーミングの形で意見をどんどん出し合うことで自分が今目をむけているものを見出し、グループのメンバーとの話し合いを通して自分の関心を掘り下げていきました。次に、出した意見の中から、「これは私たちの教会が取り組むべき問題」とグループのメンバーが全員一致で思うものを○で囲むという作業や、「どんなに時間がかかっても、私たちが力を合わせればなくせる・取り去れる」と自分が思うものを×で消すという作業を、グループごとに行いました。一連の作業を通じてグループ内で様々なことを話し合いました。大切にされたことは結論を出すことではなく、そこに到達するまでの過程だったのだと思います。自分が目を向けているものを見つめ、話し合いによって自分の関心を広げ、教会としての使命や、自分の担うべき役割について、同じ聖公会に所属する仲間と考えることができました。
【最終日】四泊五日を振り返り、自分の中で消化するためのまとめの時間を持ちました。これから一人一人が日常生活へと戻った時、どのように生きていくのかじっくりと考えました。
【全体を通して】毎晩のナイトシェアリングや節目ごとの話し合い(そしてプログラム外の時間)など、感じたことや考えたことを振り返り、内実化するための時間がたくさん設けられていました。研修会や勉強会での学びは、ともすれば消化しきれず残らないことも多いですが、このトレーニングでは、じっくりと振り返り、話し合う機会があったため、学んだものを消化して自分のものにすることができました。今回自分が得たものは何だろう?と振り返ってみると、ひとことでは言い表わすことができません。最終日にこれからの自分について思うことを書きとめた紙を読みかえすと、「自分」という言葉がたくさん書かれていました。このことが、私にとってのユースリーダーシップトレーニングを象徴しているのかもしれません。様々なことを学び、考え、いろんな人といろんなことを話し合ったけれども、一番大切なのは「自分」がどうあるか、どうありたいかということなのではないかと思います。
(京都・金沢聖ヨハネ・高田あゆみ)
長野伝道区(中部)で「祈りの集い」
九月二一~二三日、長野伝道区青年会主催の『共に創る祈りの食卓~深めよう青年たちの輪~』が野辺山で行われました。イエス様と囲んだ食卓って?最後の晩餐をイメージした食卓。「光」「パンとぶどう酒」「十字架」「歌」の四つのグループに分かれ、献げるものに思いを深めるところから始まり、実際に作って祈りの食卓に献げました。
丸くなって座り、「光あれ」の言葉に続いて光グループのろうそうに火が灯されて始まりました。お互いに足を洗い合い、バイブルシェアリングの洗足の箇所を心と体で感じました。パンとぶどう酒グループが焼いたパンとジュースを隣の人から受け、分かち合いました。十字架グループからは、一本の木の幹から作った高さ一三〇??ほどの十字架が献げられ、同じ木の枝から作った三十四個の小さな十字架が全員に配られ、”私はぶどうの木、あなたがたはその枝である”のみ言葉のとおり、私たちは神様につながっているという思いが献げられました。持ち寄られた思いを分かち合えた祈りの食卓。分かち合うことの素晴らしさに感動しました。一人の持てる力は限られているが、集まるとそれぞれの賜物が生かされ豊かなものになるんだなと思いました。ほんと、主と共にいた食卓だったと思うのです。
その他にも、野辺山満喫フリーチョイスやキャンプファイヤー、キックベースなど楽しいプログラムがたくさんありました。他教区からの参加もありとても嬉しいことでした。今回できたつながりを大切に交わりをこれからも続けていけたらいいなあと思います。(上田聖ミカエル及諸天使・石田京子)
コンサートを企画
エルピスのコンサートを一一月一六日、名古屋聖マルコ教会で開催します。エルピスは聖公会信徒が中心になって結成された関東地区を中心に活動している賛美歌の演奏グループ。新しい賛美歌の創作や、賛美歌の演歌やボサノバ風の演奏と、新しい賛美の仕方を強い信仰によって発信しています。
中部では昨秋の教区フェスティバルで前夜祭や祝会の演奏で好評を得、六月の柳城短大同窓会で再来名、メンバーの再来名の希望もあり、愛岐伝道区青年会で企画することとなりました。
中部では改訂聖歌集全曲録音や野辺山での新しい歌の創作、そして、今回のコンサートと、新しい音楽で礼拝を豊かにすることができることを希望(エルピス)しています。(中部・名古屋聖マタイ・牛島達夫)
中部教区の東京「サテライト会」
大学進学や転勤等の理由により郷里を離れると、それまでに教会を通して、恵まれた親しい人間関係からも疎遠になってしまうことが多い。「サテライト会」は東京近郊に暮らしている中部教区の青年たちが、食事会という楽しいひと時をわかちあうことによって、信仰を通して与えられた友人たちの存在を確認し、いっそう活発な交流に深めることができる機会として、開催されている。七月二四日には、総勢一二名ほどで焼肉の食卓を囲んだ。思い出話や近況を話すことができて、とても充実した時を過ごしました。今後もこの「サテライト会」をいっそう活発な交流の場としたいと考えております。(サテライト会の正式名称がないので「」で囲ってあります。)(東京・聖テモテ・住田篤穂)
札幌では昨年に引き続き、超教派による青年たちのクリスマスイベントを計画中。
愛岐伝道区(中部)の青年たちが改訂聖歌全曲録音
愛岐伝道区青年たちと毎週水曜日集まりを始めてそろそろ一年。今年六月末頃、エペソの信徒への手紙を読み終わった時、教区九〇周年のために青年たちが何かできる事があるか考えました。それで、中部の二五の教会の中で信徒さんの人数があまりにも少なくて、伴奏者さえいない教会では、やはり新しい聖歌をすぐ歌うのは難しいのではないかと思い、青年たちが一緒に歌の練習をして録音することにしました。七月から始まった私たちの歌は夏を過ぎ月二回、愛岐の青年たちが多く集まる手話の会が終わった後でも集まり、一〇月になってやっと終えることが出来ました。一一八全曲を歌うには短い時間でしたが、楽しい時間でした。本当に恥ずかしいほど不十分ですが、聞いてください。その上、聞く度に青年たちを覚えてお祈りしてください。小さいけど強い少年ダビデのような、私たちになりますように。(中部・金善姫)
中部教区青年の集い
一〇月一二~一三日、小布施のスタートハウスに中部教区の青年が二〇名程集まった。まず、九月に行われた「共に創る祈りの食卓」でできた「♪気づかせてください」という歌を教区九〇周年礼拝で歌うため、その練習をした。そして夜にには、一年前の教区フェスティバルで十字架の巡礼をし、その後一人一人がどのように歩んできたか、今考えていることはどんなことかなどについて、三つのグループに分かれて話し合いの時を持った。新しい仲間との出会いや 出来事があった中で、それぞれが自分の思いを言葉にして伝えることができ、私たちの交わりが深まった感じがした。この集いをきっかけに、また新たに歩んでいきたいという力が与えられたように思う。(中部・名古屋聖マタイ・橋本友恵)
広島で平和について学ぶ
八月一四~一六日には広島で、九月一三~一五日には松山で神戸教区青年交流会のキャンプが開かれました。
二〇名以上が集った広島ではディスカッションを中心としたキャンプで、その内容は一五日の終戦記念日を挟むということもあり一五日には平和記念公園&広島平和記念資料館に行き「平和について」考え、そして話し合いました。夕にはテゼ形式による平和への祈りの時を持ちました。最終日には「なぜ、教会に若者が集まらないのか」についても話し合いました。
松山では教会の庭の草抜きなどの軽ワークや温泉巡り・観光とのんびりした時間を楽しみました。
(神戸・聖ヨハネ・水野宏明)
祈りってなんだ?
一〇月一一日京都教区センターにて「まったりmeeting」を行った。参加者一〇名。『Face to Face第四号』の内容について話し合われた。特集は「祈りって何だ?!」。黙想と祈りの集い、ゴスペル、日曜学校、一一月に京都聖マリア教会で青年たちのコーディネートで行われる聖餐式等々、青年たちが祈りに関連していることを体験や感じたことを中心に掲載。発行は来年三月予定。(京都・聖アグネス・西井智子)
大阪の交流会
七月一四日、芦屋聖マルコ教会にて教区青年交流会が行われた。まず青年有志により夕の祈りをささげ、その後バーベキューを楽しんだ。参加者は、神戸・京都教区から駆け付けてくれた方々も含め約三〇名。思い思いに交流を深めた。
また、数名の方々は「教会めぐり企画」ということで、朝から聖マルコ教会に足を運び、主日礼拝にも出席した。
現在、教区には「青年会」組織はないが、集まる機会は有志によってその時々で設けられる。思いついた時に誰かが何かをやる、という不定期な形にはなるが、今後とも青年一人ひとりがリーダーとなり、活動していければと願っている。(大阪・芦屋聖マルコ・錦織恵里)
ナヌムの家などを訪問
夏の恒例イベントになっている日韓聖公会青年交流キャンプは、今年で八回目。私は大学時代からこのキャンプに参加し、今年で四回目になる。
今年のキャンプは、ソウルとヨンスリの二カ所で行われた。日本人キャンパーは、学生、社会人、主婦、とユニークなメンバーでの参加となった。
ヨンスリという町は、仁川国際空港から車で約三時間の所にある自然に囲まれた静かな農村である。ここでは土砂崩れのあった道の補修作業を行った。また、村ではツアー旅行で口にする事ができない韓国の家庭料理を毎日食べさせてもらった。
二泊三日のワークキャンプを終えて、次に「ナヌムの家」を訪れた。元日本軍「慰安婦」(性奴隷)のハルモニ(高齢の女性への親しみを込めた呼び方)達が共同生活をしている所である。「ナヌム」とはハングルで「分かち合い」という意味で、そこでは元日本軍「慰安婦」のハルモニ達が仏教団体の支援を受けながら、文字通りの共同生活を送っている。私達がこれまで教科書で学んだ従軍慰安婦の問題は、ハルモニの実際の体験を聞くやいなや、あれは日本軍からのみの見方の話しだという事が分かった。本当にショックである。ハルモニ達が必死で歴史を正そうとしている姿にハッとした。自分達のおじいちゃん達が起こしたこの問題を、知らんふりする事ができるだろうか?人としてまた、共に生きていく為にはとても大事な問題ではないだろうか?
毎年、青年キャンプに参加する度に課題を持ち帰ってくる。でも、日本人の悪いクセなのか日々の生活の忙しさに、忘れてしまいがちである。
私は、今度のキャンプに参加して、人と人が共に生きる為にはどうあるべきか、何が必要なのかという事を思った。いまいち私には、努力も強さも足りない。世界中にはさまざまな問題が多くあるが、まずは、この目で見てきたものからしっかり考えてみたい。次は日本での開催予定である。来年また会う韓国人キャンパーと韓国語で語り合えるようになりたい。そして、ハルモニ達の話を今度は通訳なしで、もう一度自分の耳と心で聞きたい。そこからまた違う何かが生まれるにちがいない。
(沖縄・北谷諸魂・呉屋淳子)
東北教区再始動に向け
教区の青年活動はここ二~三年の間は休止状態であったが、八月九~一一日に福島県磯山で開催された教区修養会では青年達が久々に集まることができた。なかなか普段は会えないけれども、青年達の絆の強さを再確認した一時でもあった。これから新たな青年活動に向けて、みんなで協力しあいながら、歩みを進めていきたいと思っている。東北教区が、いつも希望の内に歩んでいくことが出来るように、皆様のお祈りをお願いいたします。(東北・福島聖ステパノ・聖職候補生・越山哲也)
11月9日、淀川河川敷公園で、京都・大阪・神戸教区の青年たちによるサッカー大会を開催。
SCM現場研修
毎年、大阪生野・釜ケ崎で行われているSCM現場研修。毎年聖公会の青年たちも多数参加しているが、来年も三月八~一六日に行われる予定。
小山研修所で
八月二二~二五日、北関東教区の教役者と信徒の有志による小山研修所ワークキャンプが開催されました。小山研修所は、以前は男子修道院として用いられ、現在でも研修所として教区内外の人々にとっても霊的な支えとなる象徴的な場所でもあります。庭や墓地、建物の掃除、手入れなどのワーク、礼拝堂での祈りを通して、改めて私たち自身の信仰生活と向き合うことができました。また修道院時代を知る教役者から、当時の様子や修道院のなかでの祈り・生活を伺う機会を得たことは、参加者にとって非常に大きく、豊かな経験になりました。(北関東・志木聖母教会・川澄幸宏)
ガレージ作り
八月二六日~二九日、今年も南三原聖ルカ教会で青年ワークキャンプが開催されました。参加者総勢九名。去年はペンキ塗りをしましたが、今年は更に「ガテン系」色が一層濃いワーク内容。三階建てほどの高さの大木の剪定。スズメバチの巣の撤去。ガレージとヴェストリー庇の建て直し。特筆すべきはこの建て直し作業。皆で設計することから始め、スムーズとはいえないが、これまたひとつのことを成し遂げる大切なプロセスだな、と思わせられました。焦りを感じさせる最終日、そこには見事なチームワークの一群がありました。夜はバーベキュー。八月末ゆえ、他のキャンプのことをつまみに大盛り上がり。また浜辺で夜光虫の見事な発光を見ながら花火大会。しばし日常を離れ、一緒に体を使って共同作業・生活をする。充実感あふれる夏の締めくくりでした。(横浜・川崎聖パウロ・司祭・小林祐二)
大阪で報告会
一〇月六日、大阪聖パウロ教会で日韓青年交流キャンプの報告会を開催。大阪教区から参加した四名が報告・感想を語った。四人の感想で、共通するのは、キャンプが楽しくて仕方なかったこと、来年も必ず参加したいと思ったこと、このキャンプには主にある交わりがあり、だから全てが豊かだったこと。四人は表現も文章も違うが皆そう語っているように感じた。報告会に足を運んでくれたのは六名。少ない人数でも、私達が体験した主にある交わりの喜びを共に分かち合うことができたので、嬉しく思っている。(大阪・石橋聖トマス・村上恵依子)
リソースブック作りのワークショップ、比で開催
五月二四~三一日まで、フィリピンのマニラ近郊の丘にあるリトリートセンターにて、アジア太平洋学生青年週間のリソースブックを作るというワークショップが行われ、参加させていただきました。昨年までは、アジア太平洋学生青年週間はCCA-Youthが主催だったのですが、今年からはEASY Net(Ecumenical Asia-Pacific Students and Youth Network)というカトリックも含めた団体が主催となりました。フィリピンでの約一週間のワークショップには、フィリピン、インド、アメリカ、日本から全部で九名が参加し、”Peace be with you. あなたがたに平和があるように”という聖句をテーマに、現在の世界の状況とキリスト者として望む世界について考え、さらにその間にあるギャップは何であるのか、それはどうすれば取り除け、理想の世界となるのかということを話し合いました。そして、正義と平和が両方成り立つ世界をJUSTPEACE(Justice&Peace)と呼ぼうということになり、おのおのが平和や対立、不正やJUSTPEACEなどについて、詩や絵で表現したり、ワークショップなどで使えるような素材を考え、それらをまとめたものが一冊のリソースブックとなりました。
話し合いなども堅苦しいものではなく、日曜日にはリトリートセンターから外に出かけ、礼拝に行こうとしたら、礼拝堂から人が溢れている光景を目の当たりにしたり(結局、礼拝堂には入れませんでした)、フィリピン大学構内に不法占拠せざるを得ない人々と出会ったりもしました。いわゆる観光も少しして、世界文化遺産に指定されているところへも行ったりしました。すべてがフィリピン独特のゆったりとした時間の流れで、とても過ごしやすかったです。
去る一〇月一七日には、東京にある聖公会の牛込聖バルナバ教会にて、アジア・ユース・ウィークの日本での集まりがあり、様々な教派・団体から四〇名弱の方が集まりました。第一部は正義のろうそくと平和のろうそくからJUSTPEACEのろうそくに火を灯すという象徴的な礼拝から始まり、第二部では日本語に翻訳されたリソースブックの中からいくつかを用いたワークショップを行ったりしました。聖公会からも多数の参加者が集まりました。(中部・岡谷聖バルナバ・米山友美子)
一〇月一三~一四日、鹿児島にて九州教区の青年有志による平和の学びを行いました。これは、鹿児島県の大口聖公会におられる高齢の男性信徒から、戦争体験による証しを聞こうと突如企画されたもの。にもかかわらず九名が参加し、充実した学びのひとときを持つことができました。夜静かな中でその方からポツリポツリと聞く戦争体験談は、生でなければ感じることができない、まさに生きた証しでした。とくに戦闘に加わっての苦い体験から、「犬も野良犬のようにつながれていないと獣になってしまうように、人間はいつも神様とつながっていないと何をしでかすかわかりません」との言葉は、参加者の心に突き刺さりました。翌日は、高倉健主演の『ホタル』でも大変有名になった同じ鹿児島県の知覧にある特攻平和会館を見学。ここでも、一七歳から二〇歳前後の若い命が戦争によって失われていった歴史に触れ、一同静かにいのちの重さを感じました。
皆さんもこんな旅の企画、いかがですか? 九州教区の青年有志がアシスタントしますよ!(九州・戸畑聖アンデレ・司祭・柴本孝夫)
『第3回在日・日・韓キリスト青年共同研修プログラム』
日 程■二〇〇三年二月二五日~三月四日(七泊八日)
場 所■韓国北部・梅香里(めひゃんに)
内 容■
☆米軍射撃訓練場周辺農村での四日間の耕作と抗議行動、村祭りへの参加、反基地闘争と平和をテーマとした講演。
☆分断の現実を知る紀行などを通したトレーニング。行き先は、爆撃訓練がされている島の横断、朝鮮戦争時の虐殺現場、板門店(南北国境上の交渉拠点)、トラサン駅(南北縦断鉄道計画の最北駅)など。
☆「共同体」としての仲間関係を作る。
主催団体■韓国キリスト青年協議会(EYCK)・在日大韓基督教会青年会全国協議会(全協)・日本キリスト教協議会関西青年協議会(NCCY)
参加費 ■1万円(宿泊費・食費等滞在費込み)、往復渡航費は自己負担(3万円前後)。
青年委員会
日本聖公会第五三(定期)総会が五月二八~三〇日、東京の聖バルナバ教会にて開催された。その中で、「青年委員会設置の件」が提案され、可決された。前総会において、学生青年運動協力委員会は見直されることになったが、今回、二総会期(四年)の期限付きで「青年委員会」として再スタートした。委員会の役割に大きな変化はない。委員は村上恵依子さん(大阪)、池住圭さん(中部)、武藤謙一司祭(横浜)、八木正言司祭(東京)、黒田裕司祭(京都)、野村潔司祭(長・中部)の六名。